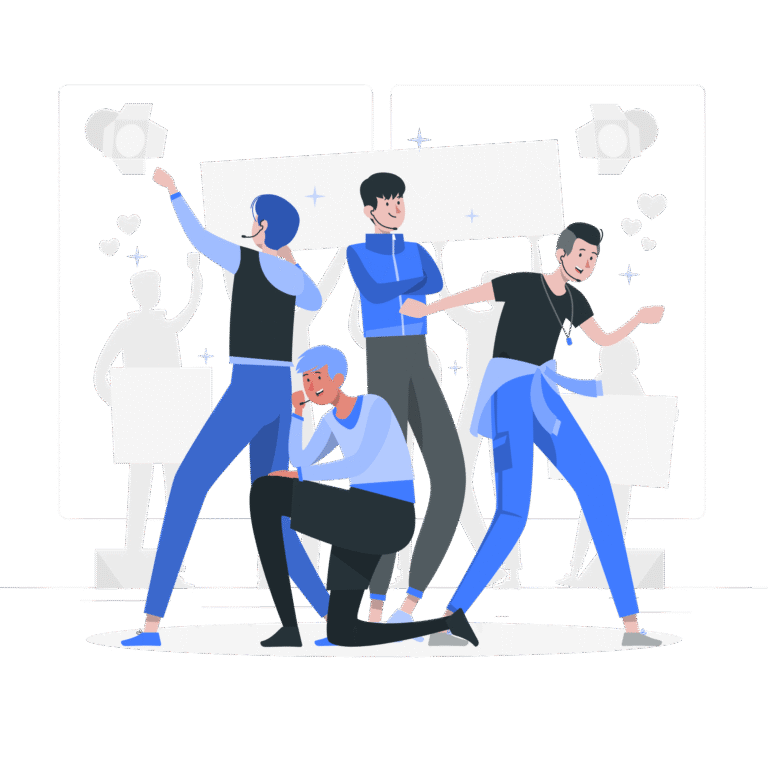「“推し”がいるだけで、毎日頑張れる気がする。」
最近よく耳にする“推し活”という言葉。
10年前なら「オタク」「趣味」として片付けられていたこの言葉が、いまでは会社員生活のモチベーションそのものになっている人も少なくありません。
私も、まあまあな年齢ですが、実は“推し”がいます。
きっかけは何気なく観たYouTube動画――そこから日々の働き方が変わりました。
今回は、そんな実体験をもとに、**「推しがいる会社員がなぜ最強なのか」**を5つの視点から語ります。
社会人はもちろん、これから社会に出る就活生にも知ってほしい、“自分を支える術”としての推し活の話です。
「推しの存在」が日々のモチベーションになる
「あと3日働けば、ライブ配信が見られる」
「給料入ったら、推しのグッズを買おう」
そんな小さな目標が、日々のエンジンになるんです。
仕事って、意外と“意味”より“目的”のほうが大事なんだと、推し活を通じて実感しました。
推しは「無条件に応援できる存在」
普段、会社では“結果”が求められます。
でも“推し”には、何があっても「頑張れ」と言える。
その無条件の応援経験は、他者への思いやりや視野の広さにもつながると感じています。
推しを語れることで「同僚との共通話題」が増える
意外と、「あのアニメ知ってるんですか?」「私もそれ好きです!」という場面が増えます。
趣味は世代や部署を超えて、人をつなげる共通項になります。
とくにリモートや雑談の減った今、**推しという“共感軸”**は貴重な存在です。
推し活で得た情報収集力・分析力は仕事にも活きる
推しのSNS更新を毎日チェック、イベント情報をいち早く入手、グッズの在庫状況を調べ尽くす――
冷静に考えると、情報処理・収集・行動力すべてがビジネスに直結しています(笑)
推し活に熱心な人ほど、仕事でも段取り上手で抜け目ない人が多い印象です。
「人生には楽しめるものがある」と知っている強さ
仕事がつらい時、理不尽な場面に出くわした時、
“推し”の存在があるだけで、心の落下防止ネットになります。
「ここが終わっても、自分には好きな世界がある」
その安心感が、働き方や生き方に余裕をもたらすのです。
まとめ
「推しがいるから、がんばれる」
これは決して軽い言葉ではなく、現代社会を生き抜く知恵のひとつだと私は思います。
やる気が出ないときも、理不尽なことがあった日も、“推し”を思い出すだけで、明日の背中を押してくれる。
社会人にとっても、就活生にとっても、“推し”は最高の相棒であり、人生の味方です。